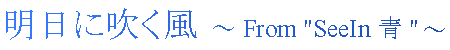
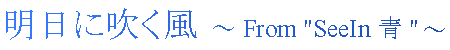
|
見上げると、深い青色の空の下を、一機のヘリコプターが飛んでいた。先程の耳障りな音は、どうやらあいつのせいらしい。 高みより眩しい陽射しを投げかける真っ白な太陽を遮るものはなく、一面の草原が風に吹かれて、波のように光って揺れた。サラサラとした音が、向こう側から俺たちの足下を通り、遠く海の方へ流れていく。 風の吹き下ろす先に、街が広がっていた。紺色の絨毯の上に、島のように浮かぶ街──『海洋都市』アンドルード。俺たちの街だ。 「わぁっ!」 風になびく長い髪の毛を片手で押さえて、琴里が感嘆の声を洩らした。自分の住んでいる街を、こんなふうに上から見下ろすのは初めてなのだろう。 「わぁ、わあぁっ! わあぁぁ!」 何やら相当嬉しいらしい。俺の手を取って、あの凶悪なまでに透き通った微笑みを浮かべる。 琴里の手の中で、いつまで経っても収まらない髪の毛が暴れ回っていた。この場所は風の通り道だ。仕方ないだろう。 その内、少し苛立った顔をして、琴里が押さえるのを放棄した。途端に、ふわっと髪の毛が舞い上がる。 一見つやつやした漆黒に思えた髪が、陽の光を受けて深い緑色に光った。 「京夜……。綺麗ですね……」 「ああ。あの中に住んでると、結構機械じみた感じがするが、こうして見てみると、思いの外自然と調和してるだろ?」 「はい……」 「結局人は、自然の中でしか暮らせないんだな。心が無意識にそれを求める……」 俺はそっと琴里の肩を抱いた。琴里は一瞬、照れたような驚いたような表情で俺を見上げたが、すぐにまた俯くように眼下の街に視線を戻して、軽く俺の肩に頭を乗せた。 風が時間を乗せて、海の向こうへ吹いて流れた。 風薫る丘の彼方に、琴里の両親──姫咲夫妻の墓があった。富士見醍吾が狂う前、まだ正常だった頃に建てたものらしい。 あの日から2年……といっても、その内の1年半は琴里にとっては止まっていた時間だったが、とにかく、俺たち二人がこうして墓参りに来るのは初めてだった。 墓は、この2年の間に来る者がなかったのか、随分風雨にさらされた跡があり、すでに落とすことができないくらいに汚れていた。それでも、琴里が持ってきた花を供えると、見違えるほど鮮やかになった。それが俺には、彼女の母親──姫咲美鈴の微笑みのように思えた。 とても優しくて、温かくて……。 きっと、彼女は自分の娘を実験台にした父、富士見醍吾を許したのだろう。 だから……。 「うっ……」 不意に、隣で手を合わせていた琴里の身体が揺らぎ、そのまま前に傾いた。 「琴里!」 俺が慌てて手を差し出すと、琴里は俺の腕の中で苦しそうに胸を押さえた。白い額に、玉のような汗が浮かんでいる。 それは、後遺症のようなものだった。富士見博士が彼女に施した実験の痕跡が、あれから2年経った今でもなお、時々こうして彼女を苦しめる。 「ほら、飲むんだ、琴里」 俺は常時携帯している薬を取り出すと、それをそっと琴里の唇に押し当てた。螺旋の配合したもので、彼女の苦しみを一時的に鎮める効果がある。 琴里は震える唇を開き、こくりとそれを喉の奥に押し込んだ。 「あ、ありがとう……」 俺の胸にぐったりと身体を預けて、琴里は弱々しく微笑んで見せた。その顔には疲れが色濃く滲んでいたが、悲壮感はまったくなかった。 経過は良好だった。確かに時々こうして、後遺症に苦しむこともあったけれど、病気……と呼んでいいものか、人間としての彼女の身体を蝕んでいた物質は、螺旋と、そして彼女の祖父である富士見博士の力によって、少しずつながら確実に消え、彼女は元の人間の身体を取り戻しつつあった。 螺旋の話では、この緑がかった髪の毛が本来の色を取り戻すのも、時間の問題らしい。 悲しむのは簡単だったが、結果だけを見れば、現実はそれほど捨てたもんじゃない。今、琴里はこうして笑っている。もしも富士見博士が彼女に実験を施さなかったら……。 そう。きっと今目の前にあるこの墓に、もう一人分の名前を刻み込むことになっていただろう。彼は彼女を助けようとした。ただ、それが行き過ぎてしまっただけなのだ。 「もう大丈夫か? 琴里」 俺が不安げに尋ねると、琴里は大きく一度息を吐いてから、にっこりと頷いた。 「はい!」 こうして生き長らえた喜びを二人で分かち合おう。 それを得るために苦しみ抜いた時間を、穏やかな瞳で振り返るために。 海洋都市が、オレンジ色の光に包まれる頃、俺と琴里はまだその丘にいた。 風はいっそう強まって、明日の方角へと吹き抜ける。 「ねぇ、京夜……」 俺の肩に身体を預けて、琴里が囁いた。自分の前に伸びた影を見つめる瞳が、陽の光をゆらゆらと跳ね返す海面をうっすらと写している。 「……なんだ?」 東の水平線から、星をその身に散りばめながら、ゆっくりと闇が押し寄せてくる。 昨日よりもまた一つ美しい夜が訪れる。 琴里はしばらく考えるような素振りをしてから、急に可笑しそうに笑って、首を振った。 「ううん。何でもない」 それから、いたずらっぽく俺の胸に顔を埋める。 きっと、とてもくだらなくて、取るに足らない些細なことを思い付いたのだろう。俺は「そうか……」と呟いてから、そんな琴里の髪をなでた。 琴里が嬉しそうに声を洩らした。 そうして、とても平和で、とても有り触れた一日が終わった。 俺たちがようやくつかんだ、ささやかな幸せの中に……。 昨日よりも輝いていた今日を乗せて、風が丘の上を吹き抜けていく。 やがて俺たちは音もなく立ち上がり、二人でその場を後にした。 夕闇の中で、草が静かに揺れ続けていた。 平穏な明日を導くように……。 いつまでも……。 いつまでも、風が草を揺らして吹き続けていた。 |